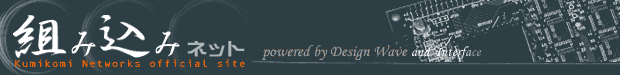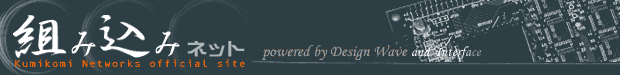|
今回のおちゃらけ:「厄を払って,役に付く」の巻
<<『梅茶で,うっしっし』プレゼント付き>>
むか〜し,むかし,あるところにおばあさんと孫娘が住んでおりました.毎年3月ごろになると,孫娘は疑問に思ったものです.「どうして,私のうちには『ひな人形』がないのだろう」と.ある年,思い切っておばあさんに尋ねてみました.すると,おばあさんはこう答えました.「ひな祭りというのはお人形のお祭りなので,お家にある人形をひな壇にのせれば,それがひな人形なのじゃ」,と….
私の家のひな人形(イメージ図)
というわけで,長い間,私の家では毎年ひな祭りの時期になると,上図のようなひな壇が床の間を飾っていたのでした.くまのぬいぐるみがちょうど対になっていたので,これを上段に置き,いわゆるおひな様とお内裏様になります.その他もろもろの人形やぬいぐるみたちがその下に適当に並べられ,五人ばやしになったり三人官女になったりするわけです.
今にして思うと,なんともほほえましくも,もの悲しい風景ですねぇ.
◆ひな人形のルーツを探る
ところで,この「ひな祭り」は,いつごろから日本人の生活に定着したのでしょうか.
もともと,中国で3月の巳の日に川に入って身を清めるという行事(上巳節)が日本に伝わり,室町時代になって貴族の女の子のお人形遊びが加わり,ひな祭りの原型ができたということです.災いを取り,身を清めるために,人形(ひとがた)を自分の身代わりにして川に流す「流しびな」は,このころのなごりです.
その後,江戸時代に入って京都御所で盛大なひな祭りが行われ,このころから庶民の間にも広まり始めたそうです.
むむ,そうすると,ひな祭りのルーツをさらに詳しく探るには,京都に行かねばなるまい!
参考文献
(1) 飯倉晴武;日本人のしきたり,青春出版社,2003年1月(初版第1版).


|